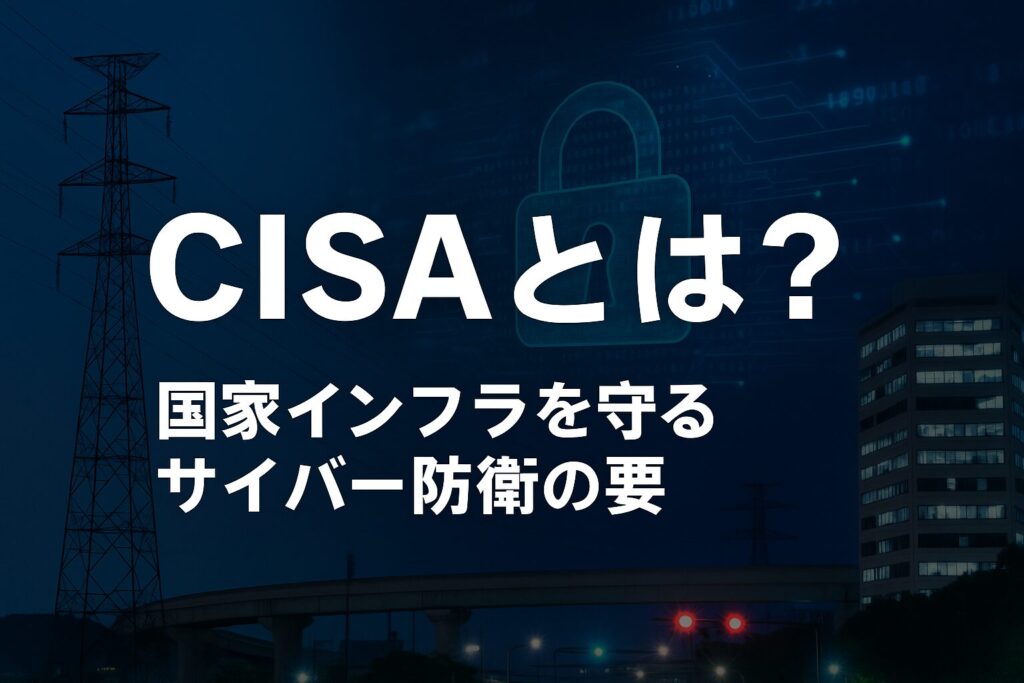
サイバー攻撃や自然災害などの脅威から、国家のインフラをどう守るか――その最前線に立つのが、アメリカの「CISA(サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁)」です。
エネルギーや医療、通信など、私たちの生活を支える重要なシステムを保護する役割を担い、近年では日本との連携も進んでいます。本記事では、CISAの役割や具体的な活動、日本との関係、そして私たちが活用できる情報を紹介します。
CISAとは?設立の背景と役割
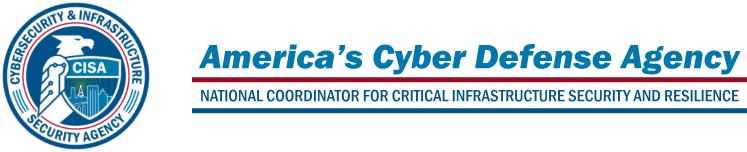
CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は、アメリカ国土安全保障省の傘下にある政府機関で、2018年に設立されました。設立の目的は、サイバー攻撃や自然災害、テロなどの脅威から重要インフラを守ることです。
CISAは「サイバーセキュリティ」と「物理的インフラの防護」の両方を担当しており、国全体の安全保障と社会機能の維持に深く関わっています。アメリカでは発電所や上下水道、交通システムなどの多くが民間運営であるため、政府と企業の橋渡し役としても重要な存在です。
▼ CISA🔗
CISAの具体的な活動内容と注目プロジェクト
CISAは日々進化する脅威に対し、さまざまな活動を展開しています。代表的なものは次の通りです。また、選挙システムの保護や5G・クラウドなど新しい技術基盤に対するセキュリティ強化にも取り組んでいます。
警告・勧告の発信
CISAは新たなサイバー脅威や脆弱性が発見されると、すぐに警告(Alert)や勧告(Advisory)を発表します。これにより、企業や自治体は迅速に対策を講じることが可能になります。
ランサムウェア対策
ランサムウェア被害の拡大に対処するため、CISAは「StopRansomware.gov」という専用サイトを設け、予防策や被害発生時の対応方法などをまとめて発信しています。
無償のセキュリティ訓練・診断サービス
CISAは重要インフラ事業者や自治体向けに、無償のサイバーセキュリティ訓練や診断サービスを提供しています。たとえば、公開サーバーの脆弱性診断や、産業用制御システム(ICS)に特化した訓練などがあります。
JCDC(共同サイバー防衛)による多国間連携
2021年に創設された「Joint Cyber Defense Collaborative(JCDC)」では、政府機関、産業界、国際組織が協力し合い、サイバー防衛体制を構築しています。ここでは脅威情報の共有、対応訓練の実施、緊急時の連携が行われています。
▼ 先日、発表された「LEV」もこの一環です🔗

日本との連携とグローバルな役割
CISAは国際的な連携にも積極的です。日本においても、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)やJPCERTなどの組織と情報共有・共同警告を行っています。
たとえば2023年には、中国系ハッカーグループ「BlackTech」に関する共同注意喚起を日米で同時に発表しました。また、港湾インフラのサイバー演習など、現場レベルでの協力も進められています。
このようにCISAはアメリカ国内にとどまらず、グローバルなサイバー安全保障の中核としても機能しています。
私たちがCISAから得られるもの
一般の人や企業も、CISAが提供する情報やツールを活用することで、サイバー攻撃への備えを強化することができます。
- セキュリティ基本ガイド:パスワードの管理や多要素認証の重要性など、初心者向けに解説。
- 無償診断ツールの活用:中小企業向けに公開されているツールで、自社の弱点を把握できる。
- アラートの確認:最新の脅威情報を把握し、すばやく対策ができる。
- 通報・相談窓口の利用:被害発生時は、CISAに連絡して支援を仰ぐことも可能。
日々の業務や生活のなかで、こうしたリソースを知っておくことが、自分や家族、組織を守る第一歩になります。
まとめ
CISAは、アメリカにおけるサイバーセキュリティとインフラ保護の中心的な存在です。その活動は日米を含む国際社会にも影響を及ぼしており、ランサムウェアや脆弱性の管理、インフラ保護といった分野で重要な役割を果たしています。
私たちもCISAの情報やサービスを活用することで、自分たちの身の回りのセキュリティを高めることができます。これからの時代、「サイバー防衛」は誰にとっても他人事ではありません。


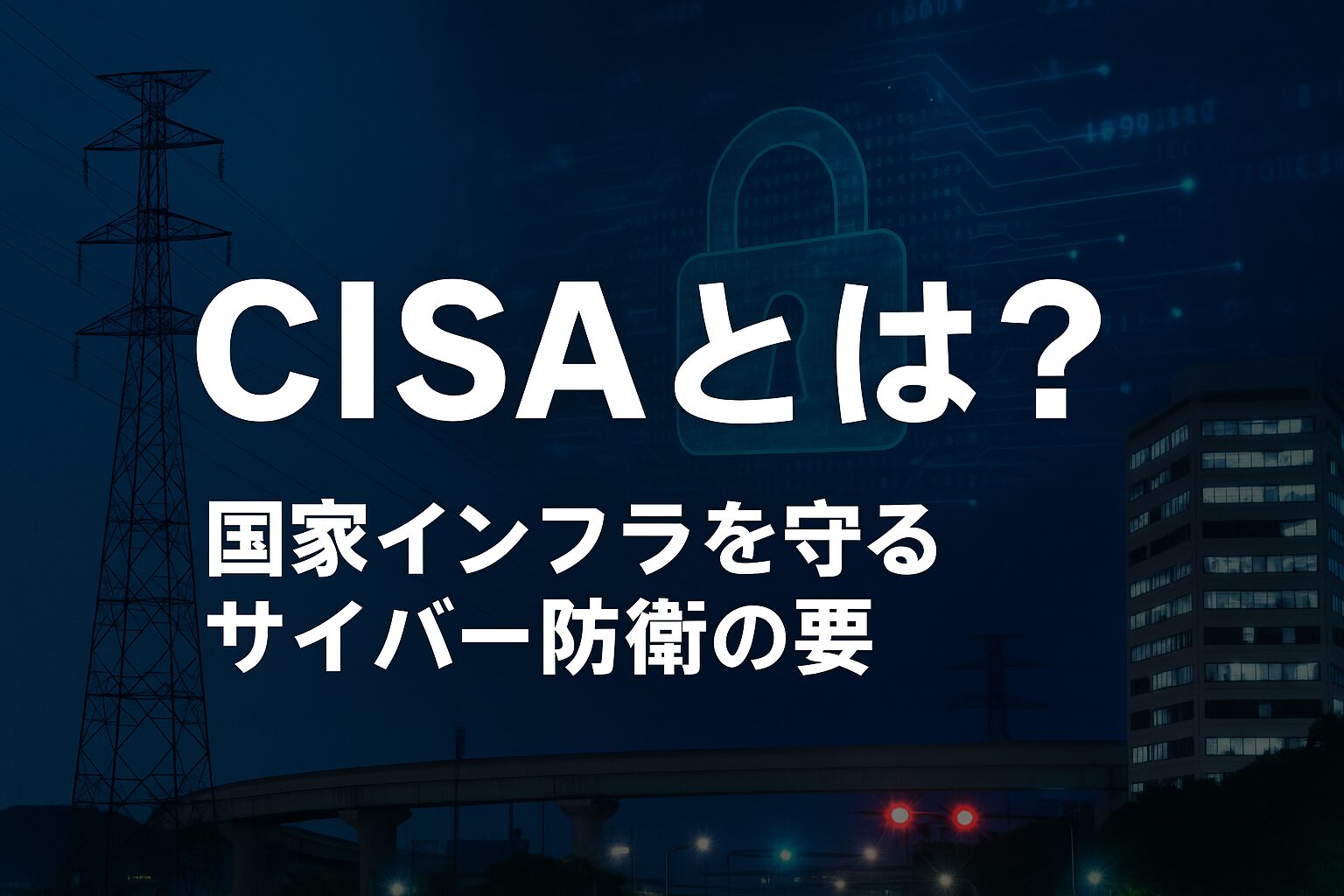


コメント